早見和真さん「あの夏の正解は」インタビュー 失った甲子園、球児に密着ノンフィクション|好書好日
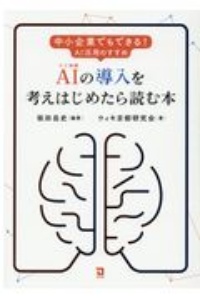

「昨日、グラウンドから寮に帰る途中、みんなでコンビニに立ち寄って早見さんの話をしたんです。 お知らせが遅れたことなど、なんかちょともらい泣きしそうになりました。
14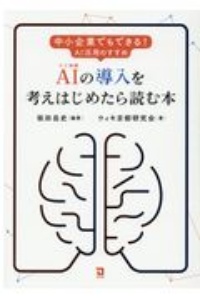

「昨日、グラウンドから寮に帰る途中、みんなでコンビニに立ち寄って早見さんの話をしたんです。 お知らせが遅れたことなど、なんかちょともらい泣きしそうになりました。
14ちゃんと前を向いている。
これを読んで、2020年、しかもまだ続いている。
(ここで早見さんご自身のエピソード話) 中瀬さん: 泣くよね!彼らのその後の進路とか、私も涙が止まらくなちゃって。
(しげまつ・きよし 作家) 単行本刊行時掲載. 【著者紹介】 早見和真(はやみ・かずまさ) 1977年神奈川県生まれ。
インターハイも、文化系の発表会も開かれず、夏は燻ったままだ。
苦闘である。
2020年『店長がバカすぎて』で本屋大賞ノミネート、『ザ・ロイヤルファミリー』でJRA賞馬事文化賞と山本周五郎賞を(史上初の)W受賞。
その締めくくりは、〈どの大人も経験したことのない三年生の夏を過ごすすべての高校生〉へのメッセージになっていた。


コロナウィルスが奪っていったものと、あとに残していったものもたくさんあるんだな、ってすごく学んだ気がします。
14強豪校の部員にとって、甲子園は決して遠い夢や憧れではない。
ひたすら歩いてきた道が突然閉ざされて立ち止まる。
強豪校でレギュラーではなく、甲子園のマウンドではなくてあのアルプスで応援する立場にあった作者だからこその視点がより彼らの想いを引き出していたように感じた。
「でもそれは、チームで存在感のある2人がつくりだした空気でしかない。
中止を理不尽だと感じ、仲間たちと何度も話し合い、その上で気づいた自分のほんとうの気持ち。 決して本音を言わない彼らからどう本心を導き出そうとしたのか、その点は間違いなく読みどころの一つだと思います。
きっと人生に一度しかない甲子園だと思って、あこがれてやまなかった舞台に立っていることだけを自覚して、自分のために野球をしてほしい」(興野優平)=朝日新聞2021年3月24日掲載. 小説と決定的に異なるのは、彼らが現在を生きている点だ。
どの選手の言葉にも重さがある。
「甲子園につながらない」各都道府県の代替大会と、無観客で開催された「甲子園交流試合」の裏側にあった現場のリアルが描かれています。


感染拡大防止のためとはいえ、戦後初めての夏の甲子園中止という大人たちの判断に球児らは言葉を失った。 合言葉を失ったのは、部員だけではない。
20うそか本当か他球場での代替開催という案が耳に入ってきたのですが、そのとき感じたのは、自分が苦しい練習に耐えてきたのはひとえに「甲子園」のためだったということです。 そして弱小校で万年補欠だった僕はひたすら泣いた。
夢中になって読んだのは、ひとりひとりにドラマがあったからだ。
だからこそ、つい「あの頃」を重ね合わせたくなるのを自制したのではないか。
題名が実に深イイ。
同調圧力の先 たどり着いた純粋性 昨年5月、その年の「夏の甲子園」である全国高校野球選手権大会がコロナ禍で中止になると発表された。 (密着している)僕を恨み倒しているはずのヤツの言葉さえ聞きたいのに、聞けなくなる」 決して誘導はせず、選手の言葉に耳を傾けた。
現役の高校球児を取材して、今の気持ちはどうですか? 早見 あの頃、あんなに恋い焦がれた野球は、結局、僕を幸せにしてはくれませんでした。
小説家の早見和真さん(43)は、2日後の本紙寄稿で、選手たちに〈今回だけは、自分の頭で正解をひねり出し、甲子園を失った最後の夏と折り合いをつけてもらいたい〉と呼びかけた。
素直に思っていることを話そう、と」。